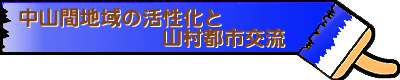
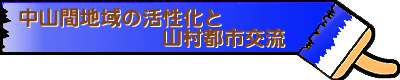
| 平成2年以降、中山間地域活性化対策という言葉をよく聞くようになった。
かつては、山村振興や山村活性化対策あるいは過疎対策などが一般的な言葉であった。 聞き慣れた「山村」には、「山の中にある村」というイメージがあり、そこには「ヤマ」と「ヒト」の馴れ合いがあり、営みがあって、特有の山村文化を形成してきている。 少なくとも「山村」には「人が住み」「暮らしている」ところという認識がある。 山村振興というとそこに住む人々の経済的、社会的向上のための施策のありようということになろう。 ところが、中山間地域というと文字どおり「山と「山」に挟まれた地域であって、「ヒト」の暮らしや生業の存在が薄らいでしまい、むしろ「人が住んでいない山間」と受け止められることが少なくなのではと心配するのは私だけであろうか。 とすると、中山間地域での活性化対策とは、山=森林の保全や河川環境の保全など、いわゆる森林の公益的機能を高度に発揮するための森林管理に関する対策のように受け止められてしまうのではないか。 もっとも、最近の農学を学ぶ学生の中には山村というと「山奥」あるいは「森林の中」と受け取るものが多く、「寂しい場所」「住み難いところ」などマイナスのイメージとしていることからすると、必要以上にこだわることはないかもしれない。 ところで、中山間地域とは農林省が採っている農業地域類型の中間農業地域(平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域で、林野率50〜80%の市町村)と山間農業地域(林野率80%以上、耕地率10%未満の市町村)を合わせた地域のことであり、自然条件の厳しい山村ないしは農山村のことである。 全国との位置づけは、総世帯数の13.3%、総人口の14.8%と低い数値であるが、市町村数においては全国の約3,250に対して55%に当たる約1,800が存在し、総土地面積では全国の約7割を占め、さらに森林面積については実に8割を占めている。 また農業生産のシェアをみると、飼料用作物57%、果樹栽培面積48%(りんご42%、柑橘類51%)、豆類38%、稲37%、野菜類35%などとなり、さらに畜産関係では、ブロイラー65%、肉用牛55%、乳用牛48%などとなっている。 わが国の国土利用において中山間地域は、農業生産の基地的存在であるとともに、国土面積の7割を占め、山林が大部分であるほか、傾斜地で農業が営まれていることなどから、山地災害や洪水の防止、水資源の確保など国土保全の面から極めて重要な役割を果たし、優れた自然景観を有していることから国民のレクリエーションの場としても重要な位置にある。 こうした中での「新農政」や「新農村基本法」及び「森林の流域管理システム」などの農林業政策は、一言でいえば、国際競争力にかなう農林業の推進ということから、経営の規模拡大によるコストの削減と機械化による法人化農林業を進めており、傾斜地が多く小規模零細で、自然条件が不利な中山間地域は切り捨てられざるを得ない。 反面、優れた自然環境を活用したグリーン・ツーリズム(都市との交流)が進められる傾向にある。 確かに、中山間地域の自然環境は条件の厳しさとは裏腹に、ストレスが鬱積した市民のレクリエーションの場として最適であるし、新鮮で、美味しい農林産物が豊富である。 とはいえ、いくら都市ニーズが中山間地域に向いているからといって無計画に受け入れることは避ける必要がある。 そこには、都市と山村の住民間による共通の理念やそれを実行する協同の連携(組織)を育てることが重要といえる。 つまり、「本物」の農林産物生産の確立とそれを基盤とした交流事業の推進であり、言い換えれば中山間地域農林業の健全な発展とそれを支え発展させる交流事業の推進が活性化の要といえ、さらにそれらを基礎条件とした上での条件不利地対策を早急に検討しなければならない時代にきている。 |